バリー・リンドンの紹介:1975年イギリス映画。キューブリック監督が撮影直前で頓挫した「ナポレオン」での資料を生かし、18世紀のヨーロッパを舞台に描く一人の男の栄達と転落の物語。原作はサッカレー。アカデミー賞では撮影、歌曲、美術、衣裳デザインの各部門で受賞。
監督:スタンリー・キューブリック 出演:ライアン・オニール(バリー・リンドン)、マリサ・ベレンソン(レディー・リンドン)、パトリック・マギー(シェバリエ)、ほか
映画「バリー・リンドン」ネタバレあらすじ結末と感想
映画「バリー・リンドン」のあらすじをネタバレ解説。予告動画、キャスト紹介、感想、レビューを掲載。ストーリーのラストまで簡単に解説します。
映画「バリー・リンドン」解説
この解説記事には映画「バリー・リンドン」のネタバレが含まれます。あらすじを結末まで解説していますので映画鑑賞前の方は閲覧をご遠慮ください。
バリー・リンドンのネタバレあらすじ:1
1750年代のアイルランド。レドモンド・バリーの父親が決闘で死にます。寡婦となった母は女手ひとつでバリーを育て上げ、今や立派に成長しました。彼にはノラという恋人ができますが、彼女は進駐してきたイギリス軍のジョン・クイン大尉にも色目を使います。大尉の実家は富裕なので、彼との結婚には彼女の家族も乗気です。大尉とノラが親しくするのに嫉妬したバリーは彼と決闘へ。バリーの弾が当たって大尉は倒れます。立会人のノラの兄弟たちは殺人の罪で逮捕されないように、バリーに逃げるようにいいますが、実際は大尉は気絶しただけでした。バリーの銃には麻で作った偽物の弾が詰めてあったのです。大尉とノラを結婚させるための一族の策略でした。
バリー・リンドンのネタバレあらすじ:2
バリーは逃亡途中で用意してあったお金を盗まれ、無一文に。仕方なくイギリス軍に志願入隊し、七年戦争に参加することになります。兵士として手柄をたてたバリーは上官から目をかけられ、出世街道に乗ったかに見えましたが、略奪行為などの規律の乱れに辟易し脱走。将校のふりをして同盟国のプロイセンへ。しかしやがて正体を見破られて今度はプロイセン軍に入ることになります。戦場でまたしても功績を上げた彼は、プロイセン警察でスパイとして働くことに。スパイの対象は、ギャンブラーのシュバリエ・ド・バリバリ。その召使となったバリーは、シュバリエの前で泣き出して自分の身分を明かしてしまいます。汚い仕事に嫌気が差したためでした。
バリー・リンドンの結末
シュヴァリエに気に入られた彼は、2重スパイとなりますが、やがて一緒にプロイセンを離れます。社交界に出入りするシュヴァリエの相棒としてイカサマ賭博で儲けた彼は、チャールズ・リンドン卿の若い妻レディー・リンドンと知り合い、彼女の愛人となります。リンドン卿が病気で死ぬと、バリーは未亡人と結婚。まんまと貴族の称号を手に入れます。しかし、前夫の子供であるバリンドン子爵との折り合いが悪く、やがて2人は決闘することに。この決闘に負けたバリーは左足を切断する大怪我を負い、イギリスも追い出されます。その後のバリーの消息は不明でした。
「バリー・リンドン」感想・レビュー
-
スタンリー・キューブリック監督の「バリー・リンドン」は、もう何度観たかわからないほど、それほど大好きな映画です。
この作品は、成り上がり貴族のバリー・リンドン(ライアン・オニール)の恋と野心、決闘と詐欺の半生を、巨大な歴史のうねりの中に描き上げた異色の大河ロマンで、ウィリアム・メイクピース・サッカレーの同名小説を原作に、18世紀ヨーロッパの片田舎や貴族社会を、風俗の細部に至るまで緻密に再現していて、もう見事としか言いようがありません。
繰り返される戦争や、何も生まない支配階級の巨大な空虚さを、くっきりと浮かび上がらせています。
柔らかな自然光を見事に生かした野外撮影も、高感度フィルムと特殊レンズで蝋燭の光の下での当時の暮らしぶりに迫った室内撮影も、文句なしの一級品だ。
めくるめくような映像。どのワンカットも緻密に計算され、構築され創造された表現美の極致を示していて、まさに息が詰まるほどの素晴らしさだ。
そして、それはまろやかで、悠々として、淡々と語られる叙事詩になっていると思います。偶然というより運命とでも呼びたい主人公バリー・リンドンの遍歴と冒険、恋、戦争、貴族社会。
一人の男が18世紀という時代の真っ只中で生きた軌跡。お話自体は、よくある出世物語だが、十分に劇的で、それでいて少しも大仰ではない。
まるで当然そうなるべく定まっていたように、バリーは彼自身の一生を生きぬく。そこには打算も情熱も苦悩も喜びも、束の間の平安も挫折も、ありとあらゆる意思と感情の葛藤があり、同時にそれは、整然と秩序立った”時代の観念”とでも言うべきものによって統一されている。
人物の動きは、ほとんど様式的といってよいほど典雅であり、だからこそ、化粧した男たちもグロテスクではない。
戦闘さえもが優雅で美しいのだ。そして、ここまで人間の一生というものを丸ごと把握し、重厚なタッチで凝視した果てには、もはや、なまじっかな感銘や主題は不要なのだ。
いわば、時代そのもの、人間の生の転移そのものが、このスタンリー・キューブリック監督がめざした表現だと思います。
そうなるともう、18世紀だとかバリー・リンドンその人だとかといった個別性は問題外だ。
ある大きな普遍性、歴史と人間の根底にある巨大な流れのようなもの、そこに目が向けられた時、この映画は地味なまでに枯れた風格を持った美しさを獲得したのだと思います。カメラ、ライティング、衣裳、演技、音楽といった方法論が、それぞれに、また相互に絡まって、時代と環境の雰囲気を創り上げ、それによって主題となる、”ある巨大な流れ”そのものを描き出す。
方法論と主題の完璧な一致が、この映画にはあると思います。


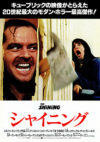








貴族は東西を問わず、白く塗りたくるのは何故?そして大した人物もいない。庶民は必死に働き子供を育て何か今の日本の国民と政治家みたいだ、貴族も政治家も無駄遣い、酒、女色ばかばかしい。もっと世の中のことを真剣に考えて謙虚になりなさい!人間ができてないよ。貴族も政治家も。