女は二度生まれるの紹介:1961年日本映画。川島雄三が大映で撮った作品の1つで、完成度の高い佳作。川島版『西鶴一代女』とも言うべき内容で、ある不見転(みずてん)芸者の暮らしぶりを男性関係を軸にしながら描いている。若尾文子がはまり役で美しい。
監督:川島雄三 出演:若尾文子(小えん)、山村聡(筒井清正)、山茶花究(矢島賢造)、フランキー堺(野崎文夫)、藤巻潤(牧純一郎)、山岡久乃(筒井圭子)、江波杏子(山脇里子)、中条静夫(田中)、上田吉二郎(猪谷先生)、高野通子(筒井敏子)、ほか
映画「女は二度生まれる」ネタバレあらすじ結末と感想
映画「女は二度生まれる」のあらすじをネタバレ解説。予告動画、キャスト紹介、感想、レビューを掲載。ストーリーのラストまで簡単に解説します。
映画「女は二度生まれる」解説
この解説記事には映画「女は二度生まれる」のネタバレが含まれます。あらすじを結末まで解説していますので映画鑑賞前の方は閲覧をご遠慮ください。
女は二度生まれるのネタバレあらすじ:起
都内の置屋に身を置く小えんは、芸者と名乗っていても体を売るだけのいわゆる不見転(みずてん)で、芸事の素養もありません。お座敷で酒の相手をした後、そのまま夜伽をするというのが仕事でした。
身寄りのない彼女にとってはそれが当たり前の身過ぎ世過ぎで、特に嘆くことでもありません。いまは特に筒井と矢島という2人の男が太客で、座敷でも外でも会う機会が増えていました。
ただ、小えんはそんな大金を落としてくれる男だけでなく、顧客の接待係として来た男へも好意を感じる事があります。
女は二度生まれるのネタバレあらすじ:承
そんな男の1人が野崎で、彼は寿司屋の板前でした。その素直な性格に惹かれた小えんはよく店を訪れ、損得抜きで彼と付き合おうとします。しかし野崎にとってあくまで彼女は顧客の夜の相手であり、まともに交際できる女性ではありません。
やがて野崎は信州のワサビ屋の入婿となり、店を辞めてしまいます。そしてもう1人、商売とは関係なく好きになった男がいました。それは近くの靖国神社で知り合った大学生の牧です。
彼はバイトに熱心な苦学生で、身寄りがなくて苦労した小えんは同情を寄せていました。彼も大学を卒業すると彼女の前から去っていきます。
女は二度生まれるのネタバレあらすじ:転
1957年に施行された売春防止法のために不見転稼業もやりにくくなっていました。ホステスに転業した小えんは誘われるまま筒井の2号になり、安アパートの部屋に引っ越します。
筒井は、美貌以外何の取り柄もない小えんの将来を憂慮する優しい男で、わざわざ金を出して小唄を習わせます。彼の思いやりに小えんも満足でしたが、成熟した体の方は彼だけでは満足できず、他の男を求めてしまいます。
そんな1人が映画館で偶然知り合った工員の孝平です。しかしこの情事がばれてこっぴどく叱られたため、以後は浮気癖を抑えます。
女は二度生まれるの結末
この安定した生活も、やがて終りが来ます。筒井が十二指腸潰瘍で倒れ、そのまま入院中に他界したのです。収入がなくなり、小えんはまた芸者稼業に戻ります。久しぶりに出た座敷では、会社員になった牧と再会。胸をときめかすのですが、彼が接待役として外人の客と寝るように頼んできたことで幻滅します。
さらに筒井の未亡人の嫌がらせもあって気分が落ち込みます。小えんは気分を直すため、やはり久しぶりに再会した孝平と上高地へ。ところが途中の車内で家族と一緒にいる野崎を見たことで、せいせいしていた気分もまた落ち込んできます。
目的地の駅に着いたものの、結局山へは孝平だけで行かせ、小えんは1人で帰りの電車を待つのです。
以上、映画「女は二度生まれる」のあらすじと結末でした。

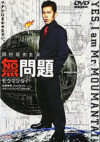



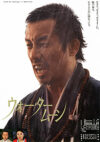





【 川島と若尾が築き上げた傑作文芸ロマン 】 雨が降りしきる「仄暗い明け方」の密室で、若い女と初老の男がなにやら会話を交わしている。 女の名は小えんと言い、瀟洒な出で立ちの「白地の絣」(かすり)の着物を身につけている。 そして白地の絣に合わせるべく「金糸をあしらった艶やかな朱の帯」がなんとも豪勢で「粋」なのである。 この「冒頭の絵」は何度見ても飽きることがない。 「カメラ」(映像)も「音」も「会話」も、すべてがしみじみ「しっぽり」としていて、とても心地良い「調和と平安」をもたらせるのである。 さて「女は二度生まれる」と言えば、これはもう若尾文子に始まり若尾文子に終わるのである。 つまりは若尾文子の魅力が満載の「玉手箱」となっているわけだ。 若尾文子はどんなカットでも絵になる「稀有な美貌」の持ち主である。その捉えようのない「奔放な美しさ」は正に規格外なのである。 そして若尾文子はその「涼し気な目」が特徴的でどこか醒めたところ、もう既に「何処かへ飛んでいる気配」さえ感じさせるのだ。 すなわち「心ここにあらず」の謎めいた「魔性の美」こそが彼女の最大の魅力なのである。 川島雄三はこの映画で若尾文子を通して、「小えん」と言う名の「憂いを帯びた哀しき女」の生きざまを「あっけらかんとしたクールなタッチで」撮り切った。 つまり前述した若尾文子の魅力の「クールビューティー」ぶりが、まさに この「映画のイメージ」に「ぴったり」とハマるのである。 戦災で親を亡くして身寄りがなく「天涯孤独」の小えん。 その小えんが「不憫」だと言って彼女に群がる「あさましき」男たち。 そしてそれらの男たちに利用され、それらの男たちを利用するしか術がない哀しき小えん。 しかしながら「男たちに抱かれても抱かれても」ついぞ「埋まらない」心の穴。 この 小えんのどこまでもいっても「満たされぬ想い」と、どうしようもない「孤独感」が映画を「見れば見るほどに」一層浮き彫りになってくる。 ところで、この作品は登場人物「一人一人の心理描写」が丁寧でとても素晴らしい。 そして小えんが出逢う男も女も一人一人みなが個性的で、必死に生きようと奮闘する「凡夫や小市民」で溢れかえっているのである。 この映画はそういった「群像劇」の側面も併せ持っているのだ。 登場人物の中でも特に面白かったのが、「山茶花究」が演じた「矢島賢造」という実業家(山師)である。 山茶花究は「クセモノの矢島」を演じて まるで水を得た魚の如く、スクリーンの中を「縦横無尽」にして「変幻自在」に泳ぎ回った。 こうして山茶花究は「何を企みナニをしでかす」か解らない「山師」の「胡散臭い矢島」を見事に怪演してみせたのである。 「傍若無人」にアメ車を乗りまわし、勢い余って「女風呂」を覗き、「斜に構えて」能書きを垂れ、常に「変化球を投じて翻弄」する「矢島=山茶花究」の存在が誠に「痛快 爽快」であった。 そして小えんは自分一人では決して生きてゆけない「哀しき女」なのであった。 それゆえに小えんは「身も心も」すべてを男たちに委ねていたのである。 中年や初老の男たちの「情婦であり玩具」であった小えんは、やがて自らの意志で「初めて男をハント」する。 そして遂に小えんは自分の意志で17歳の「純朴な孝平」を誘って「情交」を結んだのである。 小えんと孝平は互いに「接点も利害もない」二人だったからこそ「自由で」いられたのだ。 そして、結局は多くの男たちの「 山師や寿司職人や建築士たち」が 彼女の前を通り過ぎていったのである。 パトロンの筒井の死を乗り越えて、ようやく決心し覚悟を決めた小えん。 孝平と一緒に行った旅先の「島々駅」で、孝平に「この先の旅費」と「バスの切符」を渡してやり、「腕時計」すらも与えて、そこで別れて、「すっきり」と清々しい気持ちになった。 それで 最後の最後になってこれまでの自分の「人生を達観」したことで、「与えられる者」から「与える者」への「ターニングポイント/転換点」が訪れたのである。 だから「上高地行きのバス」を見送った小えんは、実はバスではなく、「自分の半生に手を振って」これまでの「人生を見送っていた」のである。 やがてバスが出た後の空っぽになった「島々駅舎」に独りで佇む小えんの姿は、「晴れ渡る信州の空」のように清々しく「愛しい」ものであった。 そしてその姿は「純朴」で穢れを知らず、涙が出るくらいに美しいものであったのだ。 このものがたりは、イプセンの「人形の家」のような、「女の自立」までの道程を描いた「或る種の文芸ロマン」なのである。