アデルの恋の物語の紹介:1975年フランス映画。『レ・ミゼラブル』で知られるヴィクトル・ユゴーの次女アデルの実話に基づく映画。一人のイギリス人士官への徹底的に一方的な恋に生きるアデルを撮影時18歳のイザベル・アジャーニが演じる。
監督:フランソワ・トリュフォー 出演者:イザベル・アジャーニ(アデル・ユゴー)、ブルース・ロビンソン(イギリス騎兵中尉、アルバート・ピンソン)、シルヴィア・マリオット(サンダース夫人)、ジョゼフ・ブラッチリー(本屋、ホイッスラー氏)、イヴリー・ギトリス(催眠術師)
映画「アデルの恋の物語」ネタバレあらすじ結末と感想
映画「アデルの恋の物語」のあらすじをネタバレ解説。予告動画、キャスト紹介、感想、レビューを掲載。ストーリーのラストまで簡単に解説します。
映画「アデルの恋の物語」解説
この解説記事には映画「アデルの恋の物語」のネタバレが含まれます。あらすじを結末まで解説していますので映画鑑賞前の方は閲覧をご遠慮ください。
アデルの恋の物語のネタバレあらすじ:起
1863年、イギリス領カナダのハリファックスに一人の若いフランス人女性、アデル・ユゴ―が到着する。港で馬車を拾いホテルまで行くが、ホテルを一目で嫌う。馭者のオブライエンの紹介でサンダース夫人の経営する下宿に落ち着くことになる。 彼女は名前を偽り、会う人ごとに矛盾する話をする。明らかなことは、彼女が関心をもっているのがハリファックスに駐屯するイギリス軍のアルバート・ピンソン中尉であることだった。彼女はかつて自分との結婚を望んだことのあるピンソンに会うべく大西洋を渡ってきたのだ。 彼女はサンダース氏にピンソンへの手紙を託すがピンソンは何も言わなかったという。手紙を開けもしなかったのだ。そして夜、19歳で夫と共に溺死した姉のレオポルディーンの死の様子の夢にアデルはうなされる。 ある日、とうとうピンソンが下宿を訪れる。しかし彼はアデルに去るように言う。彼にとってアデルとの関係は過去のことだったが、アデルはことばを尽くしてピンソンの気を引こうとする。最後は、彼が賭博の借金を返すのに使うように、父から送られた大金を渡してしまう。 ある夜、アデルはピンソンの馬車をつける。彼女はピンソンと愛人の逢瀬の現場をのぞき見し、不可思議な笑みを浮かべるのだった。
アデルの恋の物語のネタバレあらすじ:承
雪の降る日、アデルはホイッスラー氏の本屋を訪れる。長い日記を書く彼女は紙を買い足さなければならなかった。だが、本屋を出てすぐ彼女は倒れてしまう。彼女を診察した医者は、彼女の手紙の宛先から、彼女がイギリス海峡にあるガーンジー島で亡命生活を送るヴィクトル・ユゴーの次女であることに気づいてサンダース夫人にも教える。アデルはついに、ピンソンを嫌っていた父親からの結婚の許可をとりつける。男装をしてパーティー会場に乗り込みピンソンに会うが、ピンソンは改めてアデルにハリファックスを去るように言い、アデルの身勝手さをなじる。アデルはピンソンと結婚したという嘘を父への手紙に書いてさらに送金をせがむ。ところがアデルの結婚をガーンジー島の地元紙に告知させたために、ピンソンは上官にけん責を受け、父ヴィクトルも結局娘の嘘を知ることになる。ある日、ホイッスラーは、店に来たアデルに贈り物をする。彼女を喜ばせるつもりだったが、包みを開けて中身を見た彼女は怒り、これからは他の店を使うと言って出ていく。贈り物は『レ・ミゼラブル』だった。
アデルの恋の物語のネタバレあらすじ:転
アデルはピンソンへの恋のために絶望的な試みを続ける。娼婦をプレゼントしたり、彼を催眠術にかけて自分と結婚させようと催眠術師に相談したり。そして新聞でピンソンの婚約のニュースを読むと、相手の女性の家に押しかけて、ピンソンの子供がおなかにいるとまで嘘をついて婚約をつぶしてしまう。アデルは父の元に帰ると言って、終始彼女に同情的だったサンダース夫人の下宿を去る。だが、実はアデルは一文無しだった。馭者のオブライエンから教わった木賃宿に寝泊まりし、ぼろぼろの服を着てピンソンの周囲をうろつく。やがて新聞は彼女の母の死とピンソンのいる連隊の移動を告げる。
アデルの恋の物語の結末
イギリス領バルバドス島の街の黒人地区で子供たちにからかわれている異様な風体のアデルをピンソンの従卒が目撃する。彼女はピンソン夫人の名で通っていた。心身ともに病んでいるアデルを、元奴隷の過去をもつバア夫人が引き取って世話をする。ある日、街を幽霊のようにさまようアデルの後をピンソンがつける。アデルの前に姿を現し「アデル」と呼びかけるがアデルは全く気が付く様子ではなかった。バア夫人は代筆人を頼んでヴィクトル・ユゴーに、アデルの心の病について手紙で伝える。やがてバア夫人に付き添われてアデルは長い亡命生活を終えていた父の元に帰る。アデルは精神病院で日記を書き続けながら1915年まで生きる。





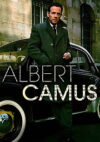





大好きなフランソワ・トリュフォー監督の「アデルの恋の物語」を繰り返し観ています。
この映画の主人公であるイザベル・アジャーニ扮するアデルの恋には悲惨さがなく、ラストに至っては、敗北のつらさより、勝利の喜びに似たものさえ感じさせるのはどうしてだろう。
自分を取り巻く現実の中に、アデルを投入してみると、トリュフォーの描きたかったものが、わかってくる。
私たちの中のアデルも、最初ピンソンへの絶ち切れぬ思いに向かって、歩いて行くだろう。
しかし、彼が決して、自分のもとへ戻って来ない事を知ると、トリュフォーのアデルと私たちの中のアデルは違ってくる。
トリュフォーのアデルの様に、私たちは進めない。
他を全く寄せつけず、ただひたすら世界の奥へ歩く彼女に、私たちはなれない。
たとえ、ピンソンを思い続けながらも、苦しみや痛みによって、この世界を終わらせざるを得なくなる。
この映画を観ていて、苦痛感にしばしば襲われるのは、トリュフォーのアデルを見ているからではなく、私たちの中のアデルを見てしまうからではないだろうか。
トリュフォーのアデルは、そして、自らの現実という壁すらも破り、もうひとつの世界へ到達する。
ピンソンの前を、何も気付かずに通り過ぎる彼女には、恋した愚かさよりも、不思議な満足感の方を見る事が出来る。
この世界で、彼女を邪魔するものは、何もない。全てが彼女自身のもの。
本物のピンソンなどは、たかが現実にすぎない。
彼女には、彼女のピンソンがいるのだ。
トリュフォーは、現実を寄せつけず、それを越えて到達するべき世界を描きたかったに違いない。
彼は、ひとつの恋を、純粋に恋のままで完結させるという、あり得ぬ事を、見事に映像化していると思う。
その結果、この映画が持ってしまった情熱—–単に、恋にかけられただけでなく、”現実と夢”を一直線にしたというところに、私は魅かれましたね。