海と毒薬の紹介:1986年日本映画。実際に行われていた米軍捕虜への生体実験を元にして描かれた遠藤周作の小説が映画化されたもの。内容的に出資者がおらず、映画化することを決定してから実際に公開されるまで17年を要した。
監督:熊井啓 出演:奥田瑛二(勝呂研究生)、渡辺謙(戸田研究生)、岡田真澄(ハットリ調査官)、成田三樹夫(柴田助教授)、西田健(浅井助手)、神山繁(権藤教授)、ほか
映画「海と毒薬」ネタバレあらすじ結末と感想
映画「海と毒薬」のあらすじをネタバレ解説。予告動画、キャスト紹介、感想、レビューを掲載。ストーリーのラストまで簡単に解説します。
映画「海と毒薬」解説
この解説記事には映画「海と毒薬」のネタバレが含まれます。あらすじを結末まで解説していますので映画鑑賞前の方は閲覧をご遠慮ください。
海と毒薬のネタバレあらすじ:起
第二次世界大戦が終わり勝呂は留置所にいました。ハットリ調査官が勝呂を調べており、勝呂に詳しく話してほしいと詰め寄ります。勝呂はF帝大医学部の米軍捕虜8人の人体実験をオペ室で見ていた人物でした。
海と毒薬のネタバレあらすじ:承
ことの発端は医学部長の取り合いでした。候補が橋本教授と権藤教授だったのですが、権藤教授は傷を負った軍人をしっかり手厚く治療しますと言い、政府からの信頼も得ていました。それに反して橋本教授はこれと言ったアピールポイントもないので焦ります。専門は肺結核の分野だったのですがある日重度の肺結核患者であるおばはんの手術を人体実験も兼ねて執刀する予定でしたが、このタイミングで失敗したらまずいという判断で、まだ手術で治る段階であり、有名な一族の親戚である田部夫人を手術することにしました。しかし手術してもらえないと悲しむおばはんを勝呂は慰めていました。
海と毒薬のネタバレあらすじ:転
しかし田部夫人は手術は失敗し手術中に亡くなりました。しかし手術して翌日に亡くなったことにするという隠蔽工作をはかり、手術中ではないので選挙に問題はないと言いました。勝呂はその実態を見て思い悩みますが、戦争で勝呂自身疲れていることもやはり事実であり、さらにおばはんが亡くなり勝呂は悲しみのあまりどうでもよくなりました。そして橋本教授は医学部長になることはありませんでした。そんな橋本教授にある話が舞い込みました。それはアメリカ人捕虜8人の生体解剖というものでした。
海と毒薬の結末
勝呂は悩みますが同期である戸田は上司をたてるのが上手く、所詮みんな死ぬのだと気にもとめてませんでした。捕虜には「大分の病院へ行く前の体格検査」という名目だったので彼らは何の心の準備もしていなかったのです。やがて手術がはじまりましたが嫌がる捕虜を前に勝呂は棒立ちになり動けなくなりました。そんな勝呂の前で繰り広げられる人体実験は、患者じゃないという理由でコカインも使わず意識がある状態で肺を切除したり、心臓の血管を止めて心停止にして蘇生措置をしたりおぞましいものでした。しかもコカインを使ってないので手術中に捕虜がうめき声を出すのです。8人全員が生体解剖で亡くなりました。手術後戸田はこれで今後何千人の命が救えると言いますが、勝呂はいつか罰を受けると言い返しました。二人の考えが交わることはありませんでした。そして生体解剖関係者25名は絞首刑5名、その他も全員有罪判決を受けましたが、その後世界情勢が急激に変化してしまい全員釈放されたのでした。
「海と毒薬」感想・レビュー
-
この映画「海と毒薬」は、大平洋戦争の末期に、九州大学の医学部で実際にあったアメリカ軍捕虜に対する生体解剖事件を基に書かれた遠藤周作の問題作を、社会派の名匠・熊井啓監督が、極力、事実に忠実に再現している作品だ。
戦後の軍事裁判で、この生体解剖に参加した教授たちなどは有罪になっている。
まず、戦時下の大学病院の実態がシビアに描かれる。有力者からの紹介などで特別に丁重な治療を受ける患者もいるが、貧しい、いわゆる施療患者たちなどは、お上の慈悲にすがって生きているという意識の下に置かれていて、自己主張もせず、診察を受けるのにもおどおどしており、患者としての人権を尊重されているとは言い難いような状況になっているのだ。
九州を空襲して撃墜されて捕虜になったアメリカ空軍の兵士たちは、無差別爆撃で一般市民も殺しているのだから、捕虜というより戦争犯罪者だ、殺してしまえ、という考え方、空気が日本軍にはあり、軍司令部は彼らを正規の捕虜として扱えという指示をせず、あいまいな態度をとったのだ。こうした状況の中、軍医たちが野蛮な敵愾心を燃やして、生体実験を求めたのだ。
そして、大学病院の中ではお定まりの人事抗争が渦巻いていた。軍が大学に対しても大きな影響力を持っていた時代で、不利な立場に置かれた教授(田村高廣)は、保身のために軍におもねるようにして、生体実験に踏み切るのだった——。
ドラマの中心になるのは、奥田瑛二の演じる医学部研究生の勝呂で、教授の命令で彼は否応なく、生体実験の助手をつとめなければならなくなるが、ひどく苦悩し、良心の呵責に苦しみ、遂に生体実験という名の殺人に加担する事は出来ずに、その場で怯えてすくんでしまう。
一方、彼の同僚の医学部研究生の戸田(渡辺謙)は、勝呂とは対照的に、良心の呵責にこそ苦しまないものの、人間的な感性が欠如しているのではないかと悩みはするが、どうせためらったって仕様がないと腹をくくって、与えられた役割をやってのける。
調べた事実は、徹底的に正確に再現する事で知られている熊井啓監督は、手術室における当時の作業のやり方などを、極力、正確に再現して見せていて、この手術シーンがリアルに描かれていて驚いてしまう。
また、この映画の核となるのは、輸血の代わりに食塩水を注射する事がどこまで可能か、といった残酷な実験が戦争の名のもとに平然と実行されていく恐ろしさを、二人の青年医師の目を通して問いかけているところだと思う。
遠藤周作の原作は、この生体解剖事件を通して、”神と人間の問題”を追及しているのに対して、この熊井啓監督の映画化作品は、より政治的な意味合いを色濃く持っていて、”時代と人間”という社会的なテーマに焦点を絞っているように思う。
この作品で、より重要に描かれるのは、当時の”時代の雰囲気”だ。
みんなが言いたい事を言わず、周囲の情勢ばかりを気にしている時、調子のいい事を言う人間の威勢のいい言動だけが、全体を大きく動かす事になり、反対出来ない流れをつくり出す。その重苦しい、”時代の閉塞感”や、大きな”心理的圧力”が、くっきりと描き出されていると思う。

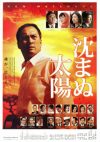
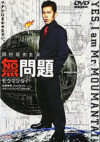








実話をベースにした、日本社会の同調圧力や建前の文化を、問題として投げかけています。